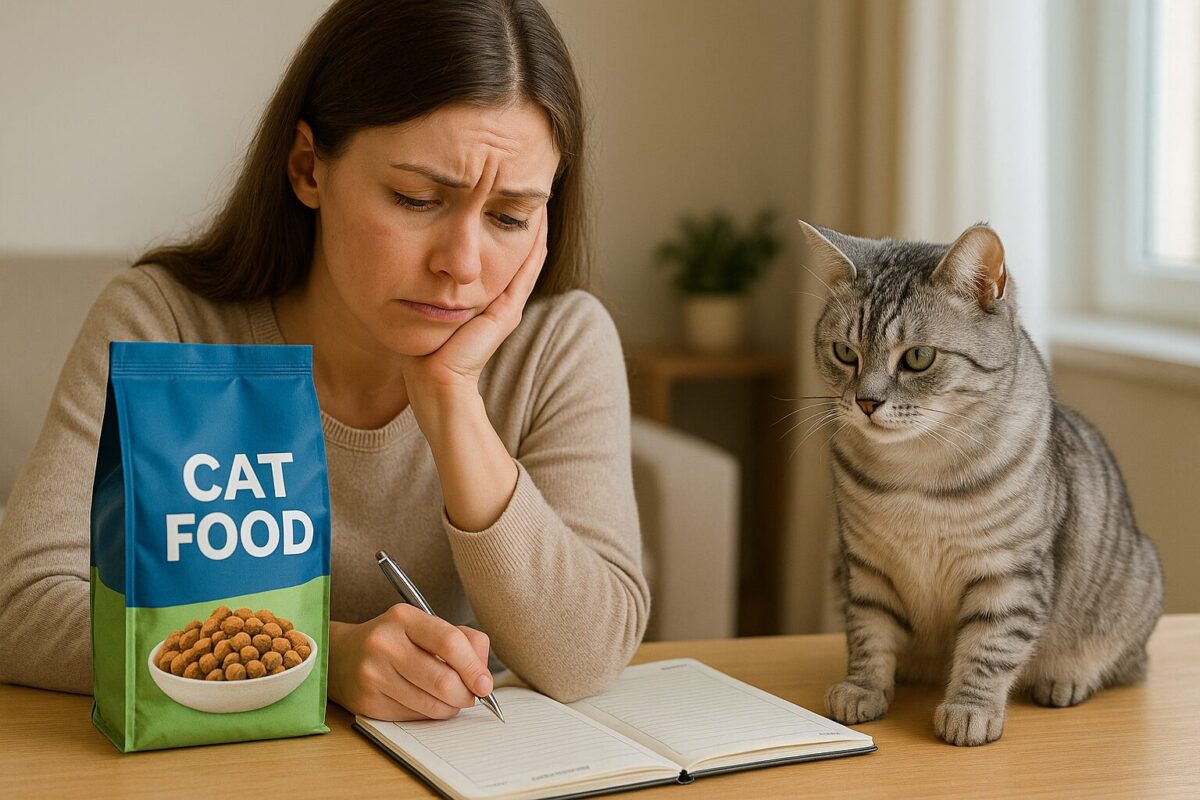キャットフードの値上げが止まらない背景
ここ数年、多くの飼い主がキャットフードの価格上昇に頭を悩ませています。特にプレミアムフードや療法食だけでなく、一般的な市販のキャットフードにおいても、1袋あたり数百円から千円単位での値上げが珍しくなくなりました。この背景には、単純な企業努力の不足ではなく、複合的な国際的・経済的要因が絡んでいます。
猫の健康を守るうえで欠かせないキャットフードは、動物性たんぱく質や脂肪、穀類、ビタミン・ミネラルなど多くの原材料を必要とします。これらの多くは輸入に依存しており、世界的な物価の高騰や円安がもろに影響を及ぼしています。さらに、製造や輸送に関わるエネルギーコストの上昇、人件費の増加、包装資材の価格高騰など、全体のコスト構造が上向きにシフトしているのが現状です。
原材料価格の高騰とその影響
まず、大きな原因のひとつが原材料価格の上昇です。キャットフードに使われる肉類(チキン、ターキー、魚など)の価格は、世界的な食糧需給バランスの変化により不安定になっています。特に2020年代に入って以降、畜産・漁業業界では飼料コストや燃料価格の上昇によって生産コストが増加し、そのしわ寄せが加工品であるキャットフードにまで及んでいます。
また、猫に必要な栄養素を補うビタミンやミネラル、サプリメントの原料も多くが中国や欧州からの輸入に頼っており、サプライチェーンの混乱や関税問題などが重なったことで仕入れ価格が数倍に跳ね上がるケースも珍しくありません。
円安と輸送コストの増加
日本国内で販売されているキャットフードの多くは、海外で製造され輸入される製品です。そのため、為替の影響は非常に大きな要素です。1ドル=120円から150円へと急激に進んだ円安は、輸入価格を押し上げる大きな原因となりました。同じ原材料・同じ製造工程でも、通貨価値の下落によって仕入れコストが一気に膨れ上がるのです。
さらに、コンテナ不足や国際物流の混乱により、輸送費も以前の2〜3倍に高騰しています。このようにして「物自体の値段」だけでなく「輸送して店頭に届くまでのコスト」も一緒に上がってしまうため、小売価格も上昇せざるを得ないのです。
製造国・メーカーごとの価格差
キャットフードの値上げは一律ではありません。特に、ヨーロッパやアメリカなど海外で製造されている製品は為替と輸送費の影響を大きく受ける一方で、国内で製造されている国産フードの価格上昇は比較的緩やかです。とはいえ、国内メーカーも原料の一部を輸入に頼っている場合が多く、いずれは国産フードも値上げの波にのまれる可能性があります。
また、同じような原材料を使用していても、メーカーの規模や仕入れルート、在庫管理の手法によってコスト吸収力は異なります。つまり「安定した供給体制を持っている企業」かどうかで、今後の価格変動の影響度に差が出てくるのです。
キャットフードの価格高騰にどう備えるか
キャットフードの値上げは飼い主にとって大きな負担ですが、猫の健康を守るために妥協はできません。そのため、価格の変動に備えて計画的な購入や商品選定が重要になります。
まず、有効な対策の一つが「まとめ買いによるコスト削減」です。割引キャンペーン時に大容量サイズを購入したり、定期購入プランを活用することで、単価を抑えることができます。また、販売店によって価格差が大きいため、複数のショップを比較検討する習慣も役立ちます。
次に検討したいのが「国産フードへの切り替え」です。前述の通り、国産製品は為替の影響を受けにくく、比較的安定した価格を維持しています。もちろん、切り替え時には猫の体質や嗜好を十分に考慮し、急激な変更によって体調を崩さないよう、徐々に移行することが求められます。
安さだけを重視しない選び方
価格が上がったからといって、単純に「もっと安いフードに変えよう」とするのはおすすめできません。安価なキャットフードの中には、かさ増しのために穀類が多く使われていたり、人工添加物が多く含まれていたりするものもあります。特にシニア猫や持病を抱えた猫には、低品質なフードが健康を悪化させる原因となることもあります。
重要なのは「価格」と「栄養価」のバランスです。一見高く感じられる製品でも、1日あたりの給餌量が少なく済む設計であれば、結果としてコスパが良いケースもあります。給餌量・原材料・栄養設計を比較しながら、愛猫に合ったフードを冷静に選ぶ姿勢が求められます。
フードローテーションとサブブランドの活用
一つのブランドや製品に固定せず、複数のフードをローテーションで使うことで、価格変動の影響を分散させることもできます。とくに主原料や栄養設計が似ている製品を数種類用意しておけば、在庫切れや値上げの際にも慌てずに対応できます。
また、ハイグレードブランドのサブラインや、同じメーカーのコスパモデルを選ぶという方法もあります。たとえば同じメーカーでも「療法食ライン」と「一般食ライン」では価格に開きがあり、後者であれば日常使いとしてより現実的な選択肢になることがあります。
猫の健康を守るためにできる工夫
価格高騰の中でも、猫の健康を維持することは最優先事項です。フード選びと同時に、食べ残しを減らす工夫や、保管方法の見直しも有効です。たとえば、密閉容器に移し替えて湿気や酸化を防ぐだけで、風味が落ちにくくなり猫の食いつきも向上します。
また、食事の時間や量を見直し、無駄に与えすぎないように管理することも節約と健康維持の両立につながります。日々の記録をつけることで、どのフードをどの程度食べているのか、無駄や嗜好の変化にも気づきやすくなります。
まとめ:猫の健康と家計のバランスをとる時代へ
キャットフードの値上げは、今後も続く可能性が高い現象です。だからこそ、ただ価格だけに左右されるのではなく、猫の健康と家計のバランスを意識した選び方と購入の工夫が求められます。飼い主としてできる備えを日常的に行いながら、愛猫にとってベストな食生活を継続していくことが、今後ますます重要になっていくでしょう。